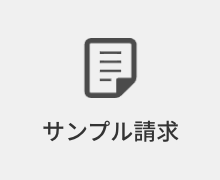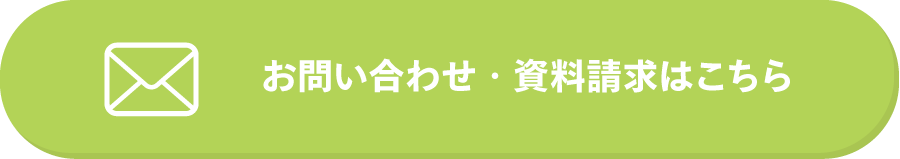ブランド価値はパッケージで決まる時代へ
.jpg)
こんにちは!太成二葉産業の広報販促室です。
今日は当社が大切にしている「パッケージによるブランディング」について、
わかりやすくお話ししたいと思います。
日々、さまざまな商品が並ぶ売場の中で
「なぜあの商品は選ばれているのか?」と感じたことはありませんか?
実はそのカギを握っているのが、“パッケージ”なんです。
このコラムでは、ブランドづくりに欠かせない
パッケージの役割と成功事例を、やさしい言葉で解説します。
最後まで読めば、きっと新しい視点が得られるはずです!
1.なぜ今パッケージが重要か
パッケージは「売れる商品」に欠かせない要素です。
店頭で最初に消費者と接する販促ツールとして、その影響力は年々高まっています。
2025年現在、SNSや口コミが購買行動に大きく関与する一方で、実店舗での商品選びは“視覚が9割”とも言われています。
つまり、手に取られるかどうかは見た目で決まるのです。
さらに、売場の変化や他社製品との競争が激化する中、「違いを一瞬で伝える工夫」が求められています。
そうした中で、ブランドの世界観を体現できるのがパッケージの強みです。
パッケージは単なる包材ではなく、顧客の記憶に残るブランド体験の入り口。
だからこそ、いま見直されているのです。
1-1.市場のコモディティ化とは
コモディティ化とは、商品が「違いのないもの」として扱われてしまう現象です。
品質や価格だけでは、選ばれ続けるのが難しくなっています。
近年、技術革新により多くの製品が似たスペック・機能を持つようになりました。
例えばスキンケア商品や清涼飲料など、どれも一定のクオリティに達しているため、消費者は迷います。
そのとき、感性に訴える要素――つまりパッケージの印象が決め手になるのです。
目に入る情報、手に取ったときの質感、そうした感覚的な要素が“選ばれる理由”になります。
だからこそ、コモディティ化に打ち勝つブランディングには、パッケージ戦略が欠かせないのです。
1-2.小売主導の売場戦略
今の売場は、小売業者が商品の価値を左右する時代です。
大型店舗やECモールでは、自社ブランド(PB)が拡大し、売場の主導権を握る構造が進んでいます。
商品を並べる場所、棚の高さ、POPやキャンペーンの有無――すべてが小売側の判断に委ねられています。
メーカー側が伝えたいメッセージも、届かないことが増えているのが現実です。
そこで、商品そのものに“語らせる”工夫が求められます。
パッケージデザインや形状、素材選びを工夫し、視線を集め、手に取らせる。
これが、小売主導の時代でも自社の魅力を伝えるための有効な手段です。
主導権が小売にある今こそ、パッケージが最も信頼できる営業担当になるのです。
2.ブランド構築に必要な視点
ブランドを築くうえで重要なのは、「伝えたい価値」がきちんと届いているかどうかです。
デザインだけで印象を操作するのではなく、顧客の心に残る“理由”を持たせることが大切です。
2025年の今、消費者は価格や機能だけでなく、共感や物語に価値を見出す傾向があります。
だからこそ、ブランド構築では「誰のために、何を叶えたいか」を明確にする必要があります。
その軸をもとに、パッケージを通じて視覚的にメッセージを伝えれば、単なる商品が“意味ある存在”へと変わるのです。
ブランド構築とは、売るための仕組みではなく、長く愛される関係性を育てる活動です。
2-1.ブランディングとは何か
ブランディングとは、企業や商品の持つ価値を意識的に「伝え、育てる」戦略です。
単にロゴや色を整えることではありません。
ターゲットに対して「これは自分のための商品だ」と感じてもらうためには、一貫した世界観とメッセージが欠かせません。
それを視覚的に伝えられるのが、パッケージの役割です。
ブランドとして認識されると、価格競争に巻き込まれにくくなり、高いリピート率と信頼を得られます。
結果として、売上の安定や流通での優遇にもつながります。
つまり、ブランディングとは“選ばれる理由”をつくる活動なのです。
2-2.ブランドのメリットとは
ブランドが確立すると、「指名買い」される状態をつくることができます。
それは企業にとって、最大の強みです。
例えば、同じような価格・品質の製品が並んでいても、ブランド力がある商品は選ばれやすくなります。
それは消費者が「安心できる」「好き」と感じているからです。
また、価格競争から脱却しやすくなる点もメリットです。
ブランドとして認知されれば、多少高くても買ってもらえる可能性が高くなります。
さらに、販路の拡大や卸先との交渉でも優位に立てるようになります。
つまり、ブランドは売上と利益の土台を支える重要な資産なのです。
3.パッケージの2つの役割
パッケージには、大きく分けて「機能性」と「訴求性」という2つの役割があります。
単に商品を包むものではなく、保護と魅力の両立が求められるツールです。
例えば食品や化粧品であれば、内容物を守る気密性や遮光性が必要です。
一方で、消費者に手に取ってもらうにはデザインやコピーの工夫が欠かせません。
この2つのバランスが崩れると、「売れない」「壊れる」といった問題が発生します。
どちらも譲れない条件であり、両立させる設計が重要なのです。
そのためには、素材選び・形状設計・印刷加工を戦略的に組み合わせる必要があります。
パッケージは、商品の価値を守りつつ、魅力を最大化する重要な存在です。
3-1.機能性と訴求性の両立
パッケージの機能性と訴求性は、どちらかに偏ると失敗の原因になります。
使いやすさと美しさのバランスが、購買行動を左右するのです。
例えば、見た目は美しいが開けにくい構造だと、リピートされません。
また、機能性に優れていてもデザインが地味すぎると、選ばれにくくなります。
最近では、環境配慮素材と高級感の両立なども求められており、特に化粧品・食品分野ではその傾向が強まっています。
私たちが提案する特殊印刷や加工技術は、触感や質感を演出しながら、パッケージ本来の機能も確保します。
魅せる・守るの両方を叶えることで、ブランドの印象も深まります。
3-2.プロモーション要素の注意点
パッケージにプロモーション要素を組み込む際は、「変更のしにくさ」に注意が必要です。
一度印刷されたメッセージは、後から差し替えることができません。
特に季節限定やキャンペーン品などは、販促の方向性が変わる可能性があります。
その際、柔軟性のないパッケージは、在庫のロスや再印刷コストにつながることも。
2025年はサステナブルへの配慮から、可変性を持たせた設計が重視されています。
例えば、ベースのデザインはブランドに集中させ、プロモーション情報はアテンションシールやPOPで補うという方法です。
こうした分離設計により、ブランディングの統一感を保ちつつ、販促にも対応できる柔軟なパッケージ運用が可能になります。
4.成功事例から学ぶ戦略
実際に売れた商品には、必ず理由があります。
その中でも「パッケージによるブランディング」に成功した例として、『KOBE香水物語』は非常に示唆に富んでいます。
この事例は、商品のコンセプトと地域の魅力をパッケージにしっかり落とし込んだことがポイントです。
さらに、見た目の美しさだけでなく、売場での展開やターゲット層への訴求もしっかり設計されていました。
つまり、ブランディングとは見た目だけの話ではないのです。
売れる仕掛けをどう設計し、どのように“共感”を形にするかが成功のカギです。
このような戦略は、他の商品開発でも参考になる視点が詰まっています。
4-1.KOBE香水物語の事例
『KOBE香水物語』は、「神戸の街の魅力を香りで表現する」という明確なコンセプトのもと誕生しました。
香りのテーマは「海」「街」「山」の3種類。神戸の情景をイメージさせるストーリー性が軸になっています。
この製品のポイントは、地元の文化と感性を“可視化”できたことです。
その結果、神戸セレクションにも選出され、認定商品として注目を集めました。
また、ターゲットは観光客や中年層の女性。パッケージの印象が購買意欲に直結する商品カテゴリだからこそ、外観への投資が効果的だったといえます。
この事例は、「誰に、何を届けたいのか」を突き詰めた結果、パッケージがブランドそのものになった好例です。
4-2.デザインに込めた意図
『KOBE香水物語』のパッケージデザインには、“感性に響く余白”がありました。
海・街・山という3テーマを、あえて抽象的に表現しすぎず、シンプルかつ上品なビジュアルに落とし込んでいます。
これは、お土産品としての汎用性を意識した工夫でもあります。
幅広い世代に受け入れられやすいよう、過度に個性的にせず、連続性や統一感でシリーズ感を演出しました。
また、3本並べると1つの絵が完成する構成も、売場での視認性と記憶定着を意識した設計です。
デザインそのものがストーリーの一部となり、消費者との心の距離を縮めてくれるのです。
まさに、パッケージが語るブランドの物語を体現した好例です。
5.感覚転移と消費行動の関係
人は見た目や香り、手触りといった感覚の印象から、商品の“中身”まで判断する傾向があります。
これを「感覚転移」と呼びます。
パッケージを手に取ったときの感触、色合い、香りの有無――これらの情報が、商品自体の価値や満足度にまで影響するのです。
つまり、内容が同じでも「印象」が違えば、評価も変わってしまうということです。
この感覚転移は、特に化粧品や飲料、香り商品など五感に訴える商材で強く表れます。
だからこそ、パッケージはただの“外装”ではなく、商品そのものの一部として設計すべきです。
感覚を制する者が、選ばれる――そんな時代に突入しています。
5-1.五感が与える印象の力
人間が外界から得る情報のうち、8割以上は視覚からだと言われています。
そこに触覚や嗅覚、聴覚、味覚が加わることで、私たちは「好き」「気になる」といった感情を抱くのです。
この感覚情報が、無意識のうちに購買行動へ影響を与えています。
たとえば、手触りの良いパッケージは「中身も丁寧につくられていそう」と感じさせますし、優しい色合いは「安心感」を生みます。
最近では、サステナブル素材や和紙風のテクスチャーなど、感触をデザインに取り入れる動きも増えています。
五感に訴えることで、言葉以上に商品イメージが伝わる。
その影響力を活かすことが、これからのブランディングに欠かせません。
5-2.セブンアップ事例の効果
感覚転移を端的に示す有名な例が、セブンアップのパッケージ変更です。
緑色の缶に黄色を15%加えた“黄緑寄り”のデザインに変えただけで、中身の味はそのままにもかかわらず「味が変わった」と感じた消費者が現れました。
彼らは「ライム感が強くなった」と口を揃え、さらには「好きだった味が変わってしまった」とクレームを入れたほどです。
このケースは、視覚情報が味覚に影響を与えることを証明した典型例です。
実際に缶の色だけが変わったにも関わらず、味の印象が大きく変わるというのは、まさに感覚転移の力を物語っています。
それほどまでに、見た目のデザインには人の感覚を左右する力があるのです。
6.まとめ
パッケージは、単なる“包むもの”ではなく、ブランド体験の入口です。
特に今のように選択肢があふれる時代では、見た目の印象ひとつで「売れるかどうか」が決まります。
コモディティ化や小売主導の売場が進む中で、企業ができる最も直接的なアプローチがパッケージによるブランディングです。
商品価値を守り、感性に訴え、ブランドの想いを“伝える”ための重要な役割を担っています。
そして、その成果は『KOBE香水物語』のような成功事例にもはっきりと表れています。
ブランドを築きたいなら、まずは「どんな印象を与えたいのか」を明確に。
そこにこそ、パッケージ戦略の出発点があるのです。
6-1.ブランディングの鍵とは
ブランディングの鍵は、「違いを一瞬で伝えること」です。
他と似ていても“なんか良さそう”と感じてもらえる印象設計が重要です。
価格や機能の比較ではなく、共感や信頼で選ばれる状態をつくること。
それがブランドの本質です。
そのためには、パッケージに一貫性・世界観・触覚的な魅力を持たせることが求められます。
顧客が商品に触れた瞬間、「このブランド、なんか好きだ」と思ってもらえたなら成功です。
ブランディングとは、心の中に“意味”を宿らせる作業です。
そしてその第一歩は、いつだって見た目から始まります。
6-2.今すぐ実践するために
すぐに取り組める第一歩は、「現状のパッケージを見直すこと」です。
商品が手に取られる瞬間をイメージしながら、何を伝えているか、伝え切れていないかをチェックしてみましょう。
ポイントは、「誰に、どんな気持ちになってほしいか」。
それが定まれば、色・形・素材・コピーなど、表現の軸が自然と見えてきます。
また、感覚転移を意識した設計も今後のキーワードです。
視覚や触覚、香りの活用など、五感に訴える要素を取り入れることで、より深いブランド体験を届けることができます。
すぐにすべてを変える必要はありません。
一つひとつ、試しながら育てていくことがブランド構築の近道です。
7.パッケージがブランドの未来を変える
パッケージは、商品を包むためのものではありません。ブランドの「顔」であり、消費者と最初に出会うストーリーテラーです。
コモディティ化や小売主導の現代において、「違いを一瞬で伝える」力こそが、選ばれる商品になるための鍵となります。
ブランド構築において、感性に訴える設計は欠かせません。
見た目の印象、手に取ったときの質感、視覚から始まる感覚転移が、“中身の価値”までも印象づける時代です。
私たち太成二葉産業は、こうした視点で企業とブランドの思いを形にするお手伝いをしてきました。
この記事が、貴社の次なる一歩のヒントになれば幸いです。
重要ポイントまとめ:
・パッケージは最も消費者に近いSPツール
・ブランディングの第一歩は「誰にどう見せたいか」を決めること
・見た目や質感が商品の印象に直結する“感覚転移”が存在
・プロモーション情報は柔軟性を持たせ、ブランド要素と分離する
・成功事例からはストーリー性と一貫した世界観が重要であることが分かる
8.よくある質問
Q1:パッケージデザインを刷新する際、最初に取り組むべきことは何ですか?
A1: まずは、ターゲット顧客の明確化とブランドコンセプトの再確認が重要です。
パッケージはブランドの「顔」として、消費者に初めて接触する要素です。そのため、誰に、どのような価値を提供したいのかを明確にし、それに基づいたデザインを検討することが必要です。
また、競合他社との差別化ポイントや、商品の特長を整理し、それらを視覚的に表現する方法を考えることも重要です。
このプロセスを通じて、ブランドの一貫性を保ちつつ、消費者に強く訴求するパッケージデザインを実現できます。
Q2:パッケージデザインの変更が売上に与える影響はどの程度ですか?
A2: パッケージデザインの変更は、消費者の購買意欲に直接影響を与える可能性があります。
例えば、視覚的に魅力的で、商品の特長やブランドの世界観を効果的に伝えるデザインは、消費者の関心を引き、購買行動を促進します。
また、パッケージの素材や形状、開閉のしやすさなどの機能性も、消費者の満足度や再購入意欲に影響を与えます。
ただし、デザインの変更が必ずしも売上の向上につながるわけではありません。ターゲット層のニーズや市場のトレンドを十分に分析し、それに基づいた戦略的なデザイン変更が求められます。
Q3:パッケージデザインを内製する場合と外部に委託する場合のメリット・デメリットは何ですか?
A3: 内製する場合、ブランドの理念や商品の特長を深く理解している自社のスタッフがデザインを手がけるため、一貫性のある表現が可能です。また、修正や変更が迅速に行える点もメリットです。
一方、外部に委託する場合、専門的な知識や経験を持つデザイナーの視点から、斬新で効果的なデザイン提案を受けることができます。市場のトレンドや消費者の嗜好を踏まえたデザインが期待できます。
ただし、外部委託では、ブランドの理念や商品の特長を正確に伝えるためのコミュニケーションが重要となります。また、コストやスケジュールの管理も必要です。
最適な選択は、プロジェクトの規模や目的、社内のリソース状況などを考慮して判断することが望ましいです。
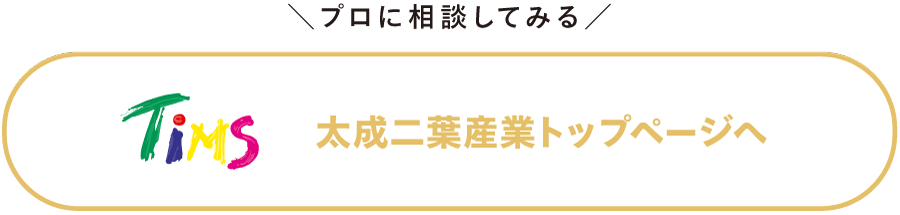
最後までお読みいただきありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。
太成二葉産業へのお問い合わせはこちらから。