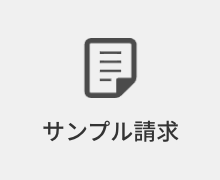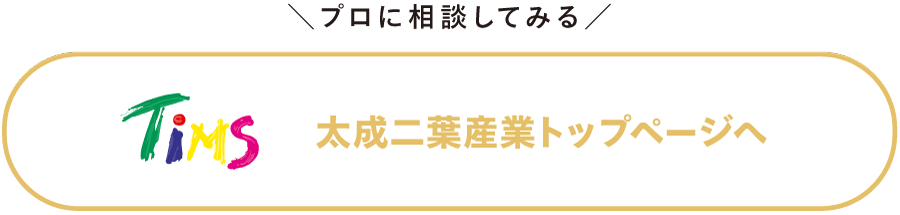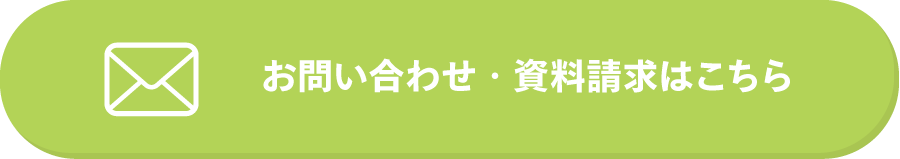印刷業の未来を変える人材育成戦略とは?現場×DX×感性がカギ
.jpg)
こんにちは!太成二葉産業の広報販促室です。
みなさんの職場では、人材育成についてどんな取り組みをされていますか?
私たち印刷業界でも、技術の進化や人手不足を背景に「育てる力」の重要性が高まっています。
新人研修、技術継承、DX対応――これらを成功に導くには、考え方と仕組みが欠かせません。
この記事では、現場の変化に向き合いながら、未来を見据えた人材育成のヒントをご紹介します。
印刷に関わるすべての方へ、参考になる内容をお届けします。
目次
1. 印刷業界に求められる変化
印刷の役割は、ただ紙に情報を載せることから、体験や価値を届ける手段へと変化しています。
需要の中心が大量生産から個別対応に移り、業務フローにも柔軟さが求められています。
オンライン受注、短納期対応、デジタル印刷など、従来のやり方だけでは対応が難しい場面が増えました。
消費者が求めるのは、スピードだけでなく、「選びたくなる印刷物」であること。
印刷会社は今、価値提供型の存在へと進化が求められています。
1-1. 紙離れと多様なニーズ
スマホやSNSの普及によって紙の利用が減る一方、印刷物に求められる役割はむしろ増えています。
「情報の伝達」ではなく「記憶に残る体験」を届けるツールとして再注目されています。
印刷に香りや質感、加工を加えることで、五感に訴えるプロモーションが可能になります。
小ロット対応やパーソナライズも、ブランドの世界観づくりに有効です。
紙の魅力は、単なる情報以上の価値を生み出せる点にあります。
1-2. デジタル対応と即納体制
注文から納品までを短くするためには、デジタルの力が欠かせません。
Web-to-Printの導入により、見積もりや校正をオンラインで完結できる企業が増えています。
印刷データの自動処理やクラウド連携も進み、従来よりもスムーズなフローが実現しました。
即納や当日発送といったニーズに応えるには、デジタル環境と現場の連携が重要になります。
今後は、紙とデジタルの両立が当たり前の時代になっていきます。
2. 技術継承と人材不足の壁
現場ではベテラン技術者の退職が相次ぎ、長年の経験や感覚が少しずつ失われています。
技術継承の課題はどの印刷会社でも感じており、人材不足とあわせて深刻な問題となっています。
ただ「後継者がいない」ではなく、「伝える仕組みがない」ことも要因です。
OJTだけに頼らず、動画やマニュアルの整備、複数人で教える体制が必要とされています。
今の若手は育て方を工夫すれば、戦力化までのスピードも早くなります。
2-1. 熟練技術の退職リスク
長年にわたって培われた色調整や加工のノウハウは、数値では表しにくい知識です。
このような熟練技術の多くは個人に属しており、引き継ぐ前に退職してしまうと取り返しがつきません。
いまはマニュアル化が進んでいますが、完全には再現できない部分も残っています。
会社として計画的に「見える化」しながら、誰でも共有できる仕組みを作ることが急務です。
経験の断絶は、生産性や品質に大きな影響を及ぼします。
2-2.「教える文化」への転換
かつては「見て覚える」のが当たり前とされていました。
しかし今の若手には、説明やフィードバックのある学びの場が必要です。
教える側も、あらためて手順や理由を整理することで技術への理解が深まります。
社内全体で育てる意識を持つことで、離職防止やチーム力の向上にもつながります。
言語化と共有を繰り返すことで、企業文化としての「教える仕組み」が根づいていきます。
3. 育成が業績を左右する時代
人材をどう育てるかによって、現場の安定や企業の成長に差が出るようになってきました。
自社の特性や方向性を理解した上で、教育に戦略的に取り組むことが求められています。
とくに若手の成長スピードは速く、育て方次第で業務改善や組織改革を担う存在になります。
ただ人手を増やすのではなく、一人ひとりの力を最大限に引き出す仕組みづくりが重要です。
育成はコストではなく、企業価値を高める投資と考えるべきです。
3-1. 若手が現場を変えていく
最新技術に慣れている若手は、DXや自動化にも柔軟に対応できます。
従来のやり方にとらわれず、改善や提案にも積極的な傾向があります。
現場を理解した上で、より良いやり方を考える姿勢は、会社全体に良い影響をもたらします。
世代交代というより、新しい価値観が組織に入ることで、変化が加速していくのです。
若手の意見を吸い上げられる仕組みを整えることも大切です。
3-2. 現場発のDX推進事例
導入だけで終わるデジタルツールは少なくありません。
成果を上げている会社は、現場の社員が「なぜ使うか」を理解し、改善に活かしています。
ある印刷会社では、現場主導で業務フローを見直し、工程の可視化と無駄の削減に成功しました。
トップダウンではなく、現場が主体となったDXこそが根づくポイントです。
小さな取り組みから始めて、少しずつ成功体験を広げていくことが効果的です。
4. 次世代に必要な3つの力
これからの印刷業を支える人材には、幅広い視点と実行力が求められます。
専門知識だけでなく、顧客や社会のニーズを捉え、チームを巻き込む力が重要です。
とくに現場の中核を担う若手リーダーには、「企画力」「ITリテラシー」「人材育成」の3つが軸になります。
どれか1つではなく、バランスよく磨くことで、変化に強い組織をつくることができます。
学び続ける姿勢こそが、次世代リーダーの資質といえるでしょう。
4-1. 企画とマーケ視点の強化
ただ印刷するだけでは、選ばれる理由になりません。
どんな目的で、どんな効果を期待されているのかを読み取る力が必要です。
販促物の制作でも、SNSキャンペーンや購買導線を意識した提案が価値につながります。
パッケージやPOPの案件では、顧客のブランドづくりをサポートする力が問われます。
印刷はマーケティングの一部であるという意識を持つことが成果につながります。
4-2. 技術とITの融合力
印刷工程においても、ITとの連携はますます重要になっています。
刷版・出力・検査など、あらゆる場面でデジタル管理が進んでいます。
業務フローの自動化やクラウド連携を理解することで、作業の精度と効率が上がります。
現場の知識とシステムの知識、両方を持つことで、現実的な改善提案ができるようになります。
技術職こそITの視点を持つことが、これからの現場力を高めるポイントです。
4-3. 育成と管理の両立力
人材が定着しない職場では、生産性や品質の維持が難しくなります。
チームを育てる視点を持つことで、自分の仕事にも余裕が生まれます。
OJTだけでなく、業務を分解して説明できる力や、フィードバックの方法も重要になります。
現場での声かけやサポートが、組織の信頼や連携を強めることにつながります。
人を育てながら成果も出せる人材が、これからの現場を引っ張っていきます。
5. 外部研修の活用メリット
人材育成を社内だけで完結させるのは難しくなっています。
とくに印刷業界では、技術の進化やデジタル対応の速さに社内教育が追いつかないケースもあります。
外部研修には、専門性と客観性をもった学びの機会があり、現場にない視点を補ってくれます。
講師による直接指導、他社との情報交換、実践型カリキュラムなどは即戦力の育成に有効です。
会社全体の底上げを図るには、外部との連携が不可欠になっています。
5-1. 社内OJTの限界とは
現場の忙しさが続くと、丁寧な教育の時間が取れない状況が起こりやすくなります。
ベテランが教える側に回ることで、作業の効率が下がることも避けられません。
教える内容が属人的になったり、教える人によって差が出たりする課題も残っています。
知識や技術を体系的に伝えるには、やり方の見直しが必要です。
OJTだけでは補いきれない部分こそ、外部研修を活用する意義があります。
5-2. 専門機関で即戦力育成
外部研修では、印刷工程や営業提案などを実践形式で学べるプログラムが増えています。
特にJAGATなどの業界団体は、印刷業に特化したカリキュラムを提供しており効果的です。
クライアントとの打ち合わせ、仕様書作成、提案資料の作成など、リアルな業務を想定した内容が中心です。
すぐに現場で使えるスキルを短期間で習得できる点は、若手の自信にもつながります。
社内教育と組み合わせることで、より高い効果を生み出せます。
6. 新人育成は体験が鍵
新入社員を早期に戦力化するには、ただ知識を教えるだけでは足りません。
実際の現場で起こることを自分の手で体験することで、理解や応用力が高まっていきます。
とくに印刷業の仕事は流れが多く、人や物との関わりも複雑です。
そうした全体像を肌で感じることが、本人の成長に直結します。
体験によって得た気づきや成功体験は、仕事への自信につながります。
6-1. 座学よりアクティブ体験
資料を読むだけ、話を聞くだけの研修では記憶に残りにくい傾向があります。
一方で、実際に考えて動く研修では、自分で行動した分だけ理解が深まります。
協働や対話を取り入れた形式なら、仲間との関係も育まれやすくなります。
若手社員にとっては、失敗を恐れず試せる場が重要です。
学びをそのまま現場に活かせるアクティブな体験は、今の時代に合った育成手法です。
6-2. 営業研修の成功例紹介
例えば、日本印刷技術協会(JAGAT)が実施する営業研修では、実在する店舗の課題に対して提案を行います。
飲食店や小売店との連携で、企画から納品までの流れをリアルに体験できるのが特長です。
ヒアリング、プレゼン、見積書作成、印刷設計までを通しで学べるため、実務感覚が身につきます。
現場で何が求められているかを知る貴重な機会になっています。
新入社員のモチベーション維持と定着にも効果的なプログラムです。
7. 感性と設備の両立を目指す
どれだけ設備が進化しても、最終的な印刷品質を決めるのは“人の目”です。
とくに色に関する判断は、数値だけで決められるものではありません。
感性や経験からくる判断力と、センサーによる検査の精度。
この両方をバランスよく組み合わせることで、安定した品質とスピードの両立が可能になります。
感覚とテクノロジーを融合させた運用が、印刷会社の競争力になります。
7-1. 色再現に欠かせぬ経験値
アート系や高級品の印刷では、色のわずかな差が仕上がりに影響を与えます。
こうした繊細な色表現には、数値では測れない“感覚”が必要です。
長年の経験によって身についた視覚の判断力が、色の深みや品位を左右します。
見本との誤差を自らの目で調整しながら刷り上げていく仕事は、技術というより職人技です。
この領域は、若手への丁寧な指導と実践を通じて受け継ぐ必要があります。
7-2. センシング技術の導入効果
近年、多くの工場で印刷や製本の工程にセンシング技術が導入されています。
紙面の色濃度や汚れ、断裁ズレなどを自動で検知し、リアルタイムで修正する仕組みです。
これにより人の目では見落としやすいミスを減らし、作業者の負担も軽減できます。
不良率の低下やスピードアップにもつながり、納期対応力も向上しました。
数値で管理できる範囲を広げることで、感性の部分に集中できる環境づくりが進んでいます。
8. 企業の対応力が未来を決める
市場や社会が大きく変化する中で、柔軟に対応できる企業が強くなっています。
経営者や現場の判断スピードだけでなく、人づくりの考え方がその差を広げている要因です。
今後は、教育方針や育成方法の見直しが組織の生産性を大きく左右します。
何を学ばせ、どの領域に投資すべきかを見極める力が、企業の未来を左右する判断基準になりつつあります。
外部の知見も取り入れながら、社内の人材戦略を更新していくことが必要です。
8-1. 教育投資の方向を見直す
従来のように印刷技術だけを教える育成は、時代に合わなくなっています。
JAGATの調査でも、営業・企画領域への投資を重視する企業が増えています。
さらに、ITリテラシーやマーケティングを学ばせたいという声も多くなりました。
自社のサービス価値を高めるためには、印刷以外の知識を持つ人材の育成が求められています。
教育は「誰に、何を、なぜ学ばせるか」を再設計するところから始まります。
8-2. 助成金や外部制度も活用
育成を強化したいと考えていても、コストや時間の壁に悩む中小企業は少なくありません。
そうした課題には、各種の助成金制度が活用できます。
たとえば、人材開発支援助成金は、外部研修の費用を一部補助してくれる制度です。
東京都では、デジタルスキル習得を目的とした支援制度も広がっています。
公的制度を上手に活かすことで、育成へのハードルを下げることが可能です。
9. 変化に応える人づくりが成長を生む
印刷業界は今、技術・働き方・価値観のすべてが大きく動いています。
その中で生き残るためには、変化にしなやかに対応できる「人材育成」が欠かせません。
必要とされるのは、現場を知りながらデジタルに強く、マーケティングの視点も持つ人材です。
社内教育だけでは補いきれない部分を外部研修でサポートし、体験型の学びで定着を促すことが効果を高めます。
一方で、熟練者の経験や感性を数値化や見える化し、設備と組み合わせて未来へつなぐ工夫も重要です。
人と設備の融合、感覚とデジタルの共存が、これからの印刷業に求められる姿といえるでしょう。
育成に本気で取り組む企業こそが、印刷の未来を切り拓いていきます。
10. よくある質問と回答
Q1:印刷業界ではどんな人材が求められていますか?
A1:単に印刷機を動かすだけのスキルではなく、「デジタル知識」「顧客視点」「現場改善力」を兼ね備えた人材が重視されています。紙×Webの提案ができる人、業務を仕組み化できる人などが、組織の成長を支える存在になっています。
Q2:人材育成は現場のOJTだけで十分ですか?
A2:OJTは大切ですが、それだけでは限界があります。現場は忙しく、体系立てて教える時間が取りづらいため、外部研修やマニュアルの整備といった「教える仕組み」も並行して必要です。育成はチームで行う意識が求められます。
Q3:中小の印刷会社でも育成投資は必要ですか?
A3:必要です。むしろ中小企業ほど一人の力が業績に直結しやすいため、早期の戦力化が重要になります。少人数でも導入しやすい外部研修や助成金制度を活用すれば、コストを抑えながら実践的な教育が可能です。
最後までお読みいただきありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。
この記事の編集・監修
桑田 督大(くわだ まさひろ) / 太成二葉産業株式会社 広報販促室
特殊印刷マーケティング歴10年。印刷×マーケティングでクライアントの商品価値を高める提案を行っています。
太成二葉産業へのお問い合わせはこちらから。