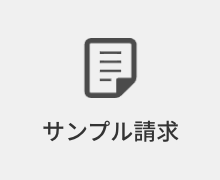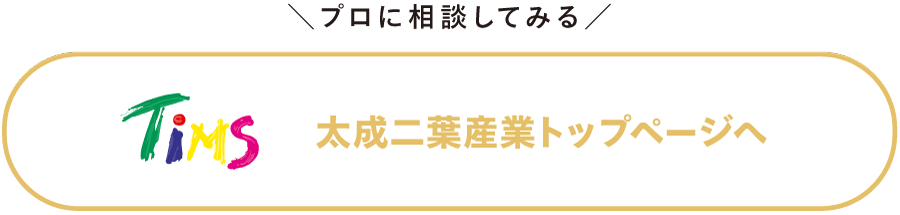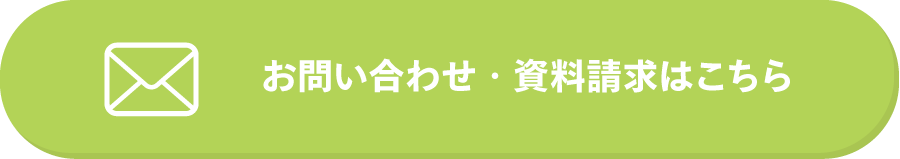売れない理由はターゲット?機会損失を防ぐ見直し術
.jpg)
こんにちは!太成二葉産業の広報販促室です。日々のマーケティング活動、お疲れさまです。
突然ですが、商品やサービスの「ターゲット設定」、なんとなく決めつけてしまっていませんか?実はその思い込みが、知らないうちに 大きなチャンスを逃している原因かもしれません。
この記事では、ターゲティングの落とし穴と、顧客ニーズを見極めるための考え方をわかりやすくご紹介します。
思い込みを手放し、選ばれるための視点を一緒に探ってみませんか?
1.ターゲティングの盲点とは
ターゲット設定は、商品やサービスの売上を左右する大切なステップです。
ところが、その判断が“思い込み”に基づいていると、大きな機会損失につながることがあります。
時代と共に価値観やライフスタイルは多様化しており、今や「性別」「年齢」「職業」といった属性だけでは不十分です。
AIによるレコメンド機能や、SNSでのトレンドが日々変わる現代においては、「どんな文脈で、どんな気分で」商品が選ばれるかがカギになります。
ターゲティングの再考は、売れない理由を外に求める前に、自社の視点を疑うことから始まります。
1-1.固定観念が招く誤解
「これは女性向けの商品だから」「うちのお客さんは高齢者が多いから」
そんなふうに決めつけてしまっていると、想像以上に広いニーズを見逃すことになります。
一人ひとりの価値観や趣味嗜好は、年齢や性別だけで語れない時代です。
たとえば最近では、男性がフラワーアレンジメント教室に通ったり、シニア世代がゲーミングチェアを購入したりと、行動パターンの多様化が進んでいます。
背景にあるのは、情報の個人最適化と「自分らしさ」を重視する社会の流れです。
固定観念から離れた柔軟な発想が、今後のターゲティングには欠かせません。
1-2.見落とされる顧客層
マーケティングにおいては、誰を“選ばないか”も重要ですが、同時に“見えていない相手”にも目を向ける必要があります。
既存顧客の枠内だけで思考が止まってしまうと、新しい市場の兆しに気づけません。
見落とされがちなのが「シーン」で商品を選ぶ人です。
商品自体には関心がなくても、「ギフトとしてちょうどいい」「職場で使えるデザインだった」など、文脈によって購買意欲が生まれます。
また、育児中の親世代や副業ワーカーといった複合的なライフスタイルを持つ層も、注目され始めています。
表面的な属性ではなく、日常のリアルな“使われ方”にこそ、新しいターゲットのヒントがあります。
2.ニーズの本質を理解する
商品やサービスが売れるかどうかは、お客様の「ニーズ」をどれだけ深く理解できるかにかかっています。
ニーズとは、単なる「欲しいもの」ではなく、「不満」や「困りごと」などの裏にある本質的な要求のことです。
売り手の目線で見ているうちは、その奥にある“なぜ欲しいのか”までたどり着けません。
大切なのは、商品を通じてどんな気持ちになりたいのか、どんな生活を叶えたいのかを見つめることです。
表面的なニーズに応えるだけでは、すぐに競合に取って代わられます。
変化の速い今こそ、根本的な価値提供が問われているといえるでしょう。
2-1.顧客ニーズの定義と種類
ニーズには「機能的なニーズ」と「情緒的なニーズ」があります。
前者は“壊れにくい”“安い”など分かりやすい欲求、後者は“安心したい”“かっこよく見られたい”など気持ちに関わるものです。
近年は後者の重要性が増しています。
多くのモノが出揃い、機能だけでは差がつかなくなってきたからです。
たとえば同じボールペンでも「就職祝いとして贈るのにふさわしいデザインか」という判断軸は、情緒的な要素にあたります。
こうした視点を持つことが、価格競争から脱却し、価値で選ばれる商品づくりへとつながります。
2-2.表層ニーズと潜在ニーズ
お客様が口にするニーズは、すでに気づいている「表層ニーズ」がほとんどです。
しかし本当に大切なのは、その奥にある「潜在ニーズ」です。
潜在ニーズは、本人もまだ気づいていない“本当の不満”や“満たされなさ”にあります。
これを捉えられるかどうかで、提案の深さや信頼の厚みが変わります。
たとえば「軽い傘が欲しい」という声の裏にあるのは、持ち歩きの煩わしさや、通勤時の手荷物を減らしたいという思いかもしれません。
ニーズの言葉だけを追うのではなく、「なぜそれが必要なのか」と問い直す視点が必要です。
3.思い込みから脱却する視点
ニーズを理解しようとする時、最も厄介なのが“自分の常識”です。
「お客様はこう思っているはず」と考えること自体が、すでにリスクだと気づくことがスタートになります。
2025年現在、消費者の行動は予測不可能なほど多様化しています。
SNSやサブスクの影響で、商品が使われる“場面”がどんどん変わってきているからです。
思い込みを手放せば、今まで見えなかった需要や、新たなコミュニケーションの糸口が見えてきます。
ニーズはつかむものではなく、「探り続けるもの」なのです。
3-1.傘に学ぶニーズの連鎖
「雨に濡れたくない」これは誰もが思うシンプルなニーズです。
しかし、そこに応えた傘が売れて終わりかといえば、そうではありません。
「もっと軽くしてほしい」「片手で開けると便利」「濡れたあとが困る」
満たしたと思った瞬間に、次のニーズが生まれる――これがニーズの連鎖です。
傘一つとっても、使う場所やシーンによって不満は変わり続けます。
つまりニーズは一度満たせば終わり、ではなく、「その先」を予測する視点が重要です。
連鎖する声に耳を傾けられる企業だけが、選ばれ続ける存在になります。
3-2.ニーズは永遠に満たされない
顧客のニーズは、決して“ゴールのある問題”ではありません。
なぜなら、満たされた瞬間に新しいニーズが生まれるからです。
たとえば、スマートフォンが高性能になればなるほど、「もっとバッテリーを長持ちさせて」「通知に邪魔されずに集中したい」といった別の要望が出てきます。
このように、ニーズは進化し続けるもの。
その変化に合わせて、商品やサービスもアップデートを重ねる必要があります。
完璧な製品を作るより、「常に改善していく姿勢」がある企業の方が、長く愛されるのはこのためです。
4.商品開発に必要な2つの視点
商品を開発するときに意識したいのは、「誰のために作るのか」という原点です。
このとき重要になるのが、「プロダクトアウト」と「マーケットイン」の視点のバランスです。
前者は、企業の技術力や発想をもとに作るスタイル。後者は、市場や顧客の声を出発点にするスタイルです。
どちらか一方に偏ると、時代やニーズの変化に置いていかれる可能性があります。
大切なのは、両者を切り分けて考えるのではなく、融合させること。
自社の強みを生かしながらも、顧客にとって意味のある価値を提供する姿勢が求められます。
4-1.プロダクトアウトの再評価
「プロダクトアウト」は作り手主導の商品開発を指します。
一見すると、顧客不在のようにも見えますが、実は使い手が気づいていない新たな価値を生む可能性がある視点です。
AppleやDysonのように、「こんな商品が欲しかった」と思わせる体験は、プロダクトアウトの成果といえます。
ただし成功の鍵は、技術力だけではなく、未来の暮らし方やトレンドへの深い理解にあります。
誰も声に出していないニーズを形にできるのは、プロダクトアウトならではの強みです。
だからこそ、過小評価せず再定義して向き合うべき視点です。
4-2.マーケットインの進化形
「マーケットイン」は、お客様の声から商品をつくる方法です。
近年では、SNS分析やレビュー抽出など、デジタル技術によって顧客理解の精度が格段に上がっています。
とはいえ、聞こえた言葉をそのまま形にしてもうまくいかないことも多いです。
言葉の裏にある「なぜそう思ったのか」を探ることが、成功の分かれ道になります。
現在では「インサイトマーケティング」や「ユーザー共創」という形で、さらに深化してきました。
表面的な要望に応えるだけでなく、心の奥にある本音を引き出す工夫が、次の一手となります。
5.ターゲット見直しの成功例
今の時代、ターゲットは“最初に決めたら終わり”ではありません。
市場の変化や生活スタイルの多様化によって、ターゲットも常に見直す必要があります。
実際、どれだけ良い商品でも、訴求先を間違えると売れません。
むしろ「誰に届けるか」を柔軟に再設定できたブランドほど、市場で成功を収めています。
過去のデータだけに頼らず、今の使われ方、これからの使われ方に目を向けてみましょう。
成功企業に共通するのは、「ターゲットを変えることを恐れない姿勢」です。
5-1.シーブリーズの転換戦略
デオドラント製品の「シーブリーズ」は、かつて海に行く若い男性をターゲットにしていました。
ところが、海離れが進み、売上は低迷。そこで思い切ってターゲットを“女子高生”に変えたのです。
それに伴い、訴求も「海で使う爽快感」から「通学中のリフレッシュ」に切り替えました。
結果、売上は8倍に跳ね上がり、定番商品として定着するまでに成長。
この成功は、「誰が使っているか」ではなく、「誰が使う可能性があるか」に着目した結果といえます。
時代の空気を読むことで、既存商品に新しい命を吹き込むことができるのです。
5-2.市場変化と柔軟な発想
現代の市場は動きが速く、2~3年前の常識がもう通用しないこともあります。
にもかかわらず、以前と同じターゲットに固執してしまう企業は少なくありません。
顧客の年齢層や性別だけでなく、使われるシーンや感情の変化にも注目すべきです。
たとえば、子ども向けだった商品が大人のリラックスグッズとして再注目された例もあります。
柔軟な発想とは、商品を変えることだけではありません。
視点を少し変えるだけで、新しい市場が見えてくる。
それが、選ばれ続けるブランドの秘訣です。
6.実践のための思考ステップ
ターゲティングやニーズの把握は、感覚や経験だけに頼るとズレが生じやすくなります。
重要なのは「思いつき」ではなく、再現性のあるプロセスを持つことです。
顧客理解を深めるためには、仮説を立てて検証する、というステップを丁寧に繰り返す必要があります。
これにより、直感では見えなかったインサイトや、価値の“兆し”を捉えることができます。
情報はあふれていますが、問いの立て方が不明確では、的確なターゲティングにはつながりません。
順序立てて思考することが、迷わずマーケティング施策を前に進めるコツです。
6-1.顧客視点でのヒアリング
顧客の声を集めるときに大切なのは、「どんなことを聞くか」よりも「どう聞くか」です。
「困っていることは何ですか?」と聞いても、表面的な答えしか返ってきません。
「なぜそれが面倒だと感じるのか」「代わりにどんな工夫をしているか」
そういった深堀りの質問が、潜在ニーズに近づく鍵になります。
また、ヒアリングの場では、話す内容だけでなく、表情や言い回しから感情を読み取る姿勢も大切です。
顧客の目線で、同じ場面を想像しながら聞くことが、“気づいていないニーズ”の手がかりになります。
6-2.ニーズの構造化と整理
顧客の声を集めたあと、その情報をどう扱うかが成果を左右します。
バラバラな意見をそのまま使っても、効果的な打ち手にはつながりません。
**重要なのは「ニーズを構造化して整理すること」**です。
「感情」「行動」「場面」の3軸で分類すると、傾向が見えやすくなります。
たとえば「外出時に手がふさがる」「混雑時は操作しづらい」などの声があれば、それは“片手で使える仕様”という共通項に落とし込めます。
このように、集めた声を意味のある形に再構築することが、精度の高いターゲティングにつながるのです。
7.機会損失を防ぐ工夫
せっかく良い商品があっても、伝え方や届け方を間違えると、チャンスを逃してしまいます。
機会損失を防ぐには、「買わなかった理由」に注目する視点が欠かせません。
なぜ選ばれなかったのか、どこで比較対象から外れたのか。
その要因を細かく洗い出すことで、改善のヒントが見えてきます。
同時に、すべての人に売ろうとするのではなく、“本当に刺さる相手”を絞り込むことも効果的です。
ムダな訴求を減らし、本当に届けたい人に価値が届けば、自然と成果はついてきます。
7-1.仮説検証の重要性
マーケティングは、思いつきではうまくいきません。
小さな仮説を立てて検証する。この積み重ねが、失敗を減らし、成功に近づく方法です。
「このターゲットにはこの表現が響くのでは」「この価格帯ならもっと反応があるかも」
そんな仮説をもとに、少しずつ打ち手を試すことで、最適な方向性が見えてきます。
結果をすぐに求めず、仮説→実行→振り返りというサイクルを回し続けることが、長期的な成果につながります。
焦らず、着実に、目の前の“なぜ”と向き合う姿勢が鍵です。
7-2.共創型マーケティングとは
最近注目されているのが、企業と顧客が一緒に価値をつくる「共創型マーケティング」です。
一方的に売る時代は終わり、使う人の声が商品を形づくる流れが主流になっています。
SNSでの投稿やレビュー、クラウドファンディングでの意見募集など、顧客と対話する機会は格段に増えました。
これを“調査データ”として捉えるのではなく、ブランドと一緒に育てる仲間として向き合うことがポイントです。
共創の姿勢を持つことで、共感も支持も生まれます。
そして結果として、長く選ばれる商品やサービスにつながっていくのです。
8.顧客に選ばれるために
どれだけ優れた商品でも、選ばれなければ存在しないのと同じです。
だからこそ、顧客の心に届くメッセージと、的確なターゲティングが必要になります。
「売るため」ではなく、「届けるため」の設計を。
そのためには、顧客のニーズを深く理解し、価値ある提案へと結びつける視点が欠かせません。
選ばれる理由は、商品そのものだけではなく、ストーリーや姿勢にも宿ります。
変化を恐れず、対話を重ね、ニーズの本質に寄り添うこと。
それが、長く選ばれ続けるブランドへの第一歩です。
8-1.顧客を「知る」技術
マーケティングにおいて、「顧客を知る」ことは最大の武器です。
ですが、それは単にアンケートをとることではありません。
本当に知るとは、顧客の感情や行動の背景まで踏み込んで理解することです。
データだけで判断せず、対話や観察を通じてリアルな気持ちをつかむ努力が必要です。
近年では、カスタマージャーニーやペルソナ設計などを活用し、より立体的に顧客像を描く手法も浸透しています。
顧客の一歩先を想像できる企業だけが、本当に必要とされる存在になれるのです。
8-2.ターゲティングの再構築へ
これからの時代、ターゲティングは“変わり続けるもの”として捉えるべきです。
一度決めたターゲットを固定せず、常に更新する感覚が求められます。
新しい生活様式や価値観、ライフスタイルの変化によって、購買行動も大きく変わってきています。
一昔前のデータや経験に頼るだけでは、的を外してしまうリスクが高まります。
ターゲティングの再構築とは、自社の視点をアップデートすることでもあります。
柔軟で客観的な姿勢こそが、これからのマーケティングの軸になるでしょう。
9.よくある質問
Q1. ターゲット設定の誤りが機会損失につながるのはなぜですか?
A1. ターゲット設定を誤ると、実際に存在する顧客層を見落とし、潜在的な売上機会を逃してしまいます。固定観念にとらわれたターゲティングは、顧客の多様なニーズを捉えきれず、結果として競合他社に顧客を奪われるリスクが高まります。顧客の購買行動やニーズは常に変化しているため、柔軟なターゲット設定が求められます。定期的な市場調査や顧客の声を反映させることで、適切なターゲティングが可能となり、機会損失を防ぐことができます。
Q2. 機会損失を防ぐために、どのような取り組みが効果的ですか?
A2. 機会損失を防ぐためには、顧客のニーズを的確に把握し、迅速かつ柔軟に対応することが重要です。具体的には、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)ツールを活用して、顧客情報を一元管理し、適切なタイミングでのアプローチを可能にします。また、部門間の連携を強化し、情報共有を徹底することで、顧客対応の漏れや重複を防ぎます。さらに、定期的な顧客満足度調査やフィードバックの収集を行い、サービスや製品の改善に活かすことも効果的です。
Q3. ターゲティングを見直す際、どのような視点が必要ですか?
A3. ターゲティングを見直す際には、顧客の多様なニーズや行動パターンを深く理解することが不可欠です。従来の性別や年齢などのデモグラフィック情報だけでなく、ライフスタイルや価値観、購買動機などのサイコグラフィック情報も考慮することで、より精度の高いターゲティングが可能になります。また、顧客との対話を通じて得られるインサイトを活用し、仮説検証を繰り返すことで、ターゲット層の再定義や新たな市場の開拓につながります。
最後までお読みいただきありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。