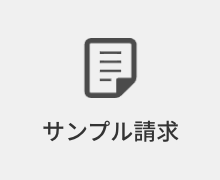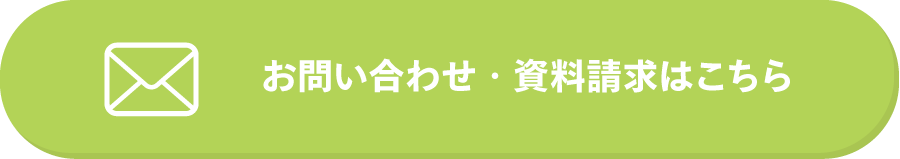訪日客を惹き付ける!3段階のインバウンド販促術
.jpg)
こんにちは!太成二葉産業の広報販促室です。
日本を訪れる外国人観光客が年々増え続けている今、
「訪日客に選ばれるプロモーションって、どうすればいいの?」と感じたことはありませんか?
この記事では、訪日前・滞在中・帰国後という3つの行動段階に分けて、
訪日客の心をつかむプロモーションのヒントをわかりやすくお伝えします。
接客や売場づくりに悩んでいる方にも、役立つ内容になっていますよ。
1.ターゲットを絞る重要性
訪日客向けのプロモーションは、最初に「誰に届けたいか」を明確にすることが重要です。
すべての国や地域を対象にしてしまうと、情報発信や商品設計がぼやけてしまい、結果として誰にも響かない可能性があります。
自社の強みと、どの国の訪日客と相性が良いかを見極めることが第一歩です。
そのためには、最新のインバウンド動向や、旅行者の消費行動データをもとに、仮説を立てるのが効果的です。
現状では中国・台湾・韓国・東南アジアの旅行者が大半を占めていますが、最近は欧米からの観光客も増えています。
観光目的や購買スタイルも異なるため、絞り込みは必要不可欠。
「すべてに向けて」ではなく、「特定の誰か」に向けた施策こそ、成果につながる鍵です。
1-1.訪日客の動向を把握する
まず把握すべきは、訪日客が「いつ」「どこで」「何をするのか」という基本的な行動パターンです。
日本政府観光局(JNTO)や観光庁、民間のマーケティングレポートなどで、旅行者の行動傾向は詳細に公開されています。
2025年現在、訪日客の主な目的は「観光」「ショッピング」「グルメ体験」の3つが中心です。
最近では、地域体験型の観光やサステナブル志向の買い物にも注目が集まっています。
たとえば、韓国からの旅行者は短期滞在が多く、都市部での買い物に集中する傾向。
一方で欧米からの訪日客は、地方の文化体験や自然に関心を示す人が増えています。
こうした動きを把握することで、プロモーションの精度がぐっと高まります。
1-2.国ごとの特性を理解する
訪日客とひとことで言っても、国によって好みも価値観も大きく異なります。
だからこそ、それぞれの文化や傾向を理解することが、効果的なプロモーションにつながります。
例えば、中国の旅行者は「指名買い」が多く、SNSや口コミで人気の商品を事前に調べてから来日します。
一方、タイやインドネシアの旅行者は、「日本らしさ」を感じられる体験やデザイン性を重視する傾向があります。
最近では、アメリカやフランスなど欧米からの訪日客も増加しており、エシカル消費や品質の高さに注目が集まっています。
単なる翻訳対応だけでなく、文化背景や価値観を理解し、それに合わせて情報を届けることが差別化につながります。
相手の視点に立つ。それがインバウンド成功の基本です。
2.訪日前の認知施策
訪日客に商品を手に取ってもらうには、訪日前の「認知」がすべての出発点です。
知られていない商品は、どれほど魅力的でも選ばれることはありません。
多くの旅行者は、日本に来る前から綿密な情報収集をしています。
SNSや動画サイト、ブログなどを通じて、買いたい商品や訪れたい店舗をリストアップしているのが現状です。
特に中華圏では「これを買う」と決めてから旅行に来る「指名買い」が一般的。
そのため、訪日前に商品の存在を知ってもらう戦略が非常に大切になります。
自社サイトだけでなく、多言語対応の観光ポータルやSNS運用も重要な施策のひとつ。
まずは知ってもらうこと、そして興味を持ってもらうことが、成功への第一歩です。
2-1.SNSと口コミを活用
今の時代、訪日前の情報収集で最も影響力があるのがSNSと口コミです。
特にInstagram、YouTube、X(旧Twitter)、小紅書(RED)など、ビジュアルとリアルな声が重視される媒体が主流となっています。
旅行前に「行きたい」「買いたい」と思わせるためには、実際の利用者の投稿やレビューが効果的です。
企業発信よりも、信頼できる個人の体験談に信頼が集まる傾向があります。
2025年はUGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用したマーケティングが当たり前となっています。
自社の商品を使ったSNS投稿を促すキャンペーンや、影響力のあるインフルエンサーとの連携がカギになります。
「第三者のおすすめ」という視点が、訪日前の印象を大きく左右します。
2-2.広告で指名買いを促す
SNSや口コミと並んで重要なのが、戦略的な広告展開です。
特に中華圏では、広告を見て購入を決める「指名買い」スタイルが根強いため、訪日前のアプローチは欠かせません。
「日本で買うべき○○」というランキングや特集広告に、自社商品が載るだけで認知が一気に高まります。
また、現地の検索エンジンやアプリ(百度・WeChat・微博など)に対応した広告出稿も、購買行動を後押しします。
最近では「12の神薬」や「必買リスト」などが話題となり、掲載商品は即完売するほどの影響力を持っています。
ターゲットに合わせた広告出稿で、旅行前に“欲しいものリスト”に入れてもらう。
それが、現地での確実な売上につながる施策です。
3.滞在中の販促施策
訪日客が実際に日本で商品を手に取るタイミングは、プロモーション成果が形になる瞬間です。
この「滞在中」にどう購買意欲を刺激できるかが、インバウンド戦略のカギになります。
言葉が通じない不安や、慣れない環境での買い物をサポートするために、店頭の視認性・わかりやすさ・信頼感が必要です。
そのためには、POPやパッケージデザイン、商品構成の工夫が大きな役割を果たします。
訪日前の認知を「購入」へとつなげるためには、目に見える工夫が重要です。
どんなに商品力があっても、伝わらなければ選ばれません。
現場での販促施策が、訪日客との最後の接点になります。
3-1.日本語POPの活用法
多言語対応が進む中で、意外にも「日本語POP」が効果を発揮するケースがあります。
日本語表記は、訪日客にとって「本物感」や「信頼性」を伝えるツールとして機能するからです。
大手ディスカウント店では、日本語のみのPOPでも外国人の購買率が高いというデータもあります。
その理由は、「日本に来ている=日本語が当たり前」という意識が働くためです。
もちろん、商品名や使用方法など、要点だけでも英語や中国語を併記するのは親切ですが、すべてを翻訳する必要はありません。
視覚的に伝わるレイアウトや、写真・アイコンでの訴求が大きな助けになります。
「伝わる」よりも「信じてもらえる」。
それがPOPの大切な役割です。
3-2.外国人向けデザイン戦略
訪日客に向けて商品を展開する際、「和」のデザインだけに頼る必要はありません。
重要なのは、そのデザインが機能性や効果を視覚的に伝えているかどうかです。
桜や富士山などのモチーフは人気ですが、場合によっては現地の消費者から「定番すぎる」と感じられることもあるため、差別化が必要です。
最近は、赤や金といった縁起の良い色を使ったパッケージが医薬品などで増えており、文化的な色彩感覚を反映したデザインが注目されています。
また、シンプルで清潔感のあるパッケージは欧米圏に好まれる傾向です。
どんな文化圏でも、商品の中身が一目で分かるデザインは強い。
その視点を持つことが、グローバルな売り場づくりに繋がります。
3-3.大容量商品の訴求方法
訪日客の購買行動には、「まとめ買い」や「お土産用の大量購入」が多く見られます。
そのため、通常よりも容量の多いパッケージや、セット売りの商品が好まれる傾向にあります。
特に中国や東南アジアからの旅行者は、家族や友人に配る前提で購入するケースが多いため、小分けになった大袋商品は重宝されます。
最近では、大箱の中に通常サイズが複数入った「ギフト向けパック」も人気です。
「爆買い」は以前より落ち着いたとはいえ、まとめて買いたいニーズは依然として健在です。
価格的なメリットに加えて、荷物整理がしやすい形状や、ギフトに適した包装も支持されるポイント。
商品形状を変えるだけで、売れ方が変わる。
滞在中の売場には、そんな可能性が眠っています。
4.帰国後のリピーター化
訪日中に商品を購入してもらえたとしても、そこで終わりではありません。
本当に大切なのは、帰国後の体験が次の訪日にどうつながるかという視点です。
商品を使った感想や、日本での体験をシェアすることで、訪日前の新たな見込み客を生み出す流れが生まれます。
そして、満足度が高ければ、リピート購入や再訪にもつながっていきます。
企業側ができるのは、情報発信の“受け皿”を用意しておくことです。
公式SNSの運用やレビュー投稿を促す仕組みがあると、自然な拡散が期待できます。
訪日中の接点を、次の来日に向けたスタートラインとして捉えることが、長期的なブランドづくりに欠かせません。
4-1.SNS拡散と口コミ効果
帰国後、訪日客が商品を使用した感想をSNSに投稿したり、家族・友人に配ったりする行動が、新たな認知のきっかけになります。
こうしたリアルな声は、次に日本へ行く人の「買いたいリスト」に直結する影響力を持ちます。
2025年現在、特に中華圏では小紅書(RED)や抖音(Douyin)といった動画系SNSでのクチコミが購買行動に直結しており、ユーザー投稿は企業広告より信頼される傾向にあります。
感想をシェアしてもらうためには、パッケージの写真映えや使って楽しい工夫も重要です。
SNSキャンペーンやハッシュタグ活用も、企業からの仕掛けとして有効。
帰国後の一言が、次の購買を呼び込む最高のプロモーションになります。
4-2.再来訪への動線設計
満足度の高い体験ができた訪日客は、「また行きたい」「また買いたい」と自然に思うようになります。
この気持ちを逃さず、再訪につながる“次のステップ”を設計しておくことが大切です。
具体的には、自社の公式アカウントをフォローしてもらう導線や、次回使えるデジタルクーポンの提供などが有効です。
また、帰国後も使える越境ECの案内を通じて、「次の訪日前に再び接点が持てる」状態をつくることができます。
こうした取り組みによって、「次もここで買おう」「今度は友人と一緒に行こう」という動機が生まれます。
再来訪を意識した動線設計は、単発の売上を継続的な関係に変える第一歩です。
5.訪日客と日本人客対応
インバウンド対応が進む一方で、日本人客への配慮も忘れてはいけません。
訪日客を優先しすぎると、常連客の不満や離反を招くことがあります。
2025年現在、外国人観光客の増加により、レジ待ちや施設の混雑が課題となっており、「買いづらさ」「居心地の悪さ」を感じる日本人も少なくありません。
この問題は、接客や導線、空間の工夫で改善できます。
どちらかに偏るのではなく、両方の満足度を保つ設計が必要です。
売上やブランドの継続性を考えるなら、インバウンドと国内顧客の“共存”こそが理想のかたちです。
5-1.接客バランスの工夫
言語や文化の違いに対応するため、訪日客向けの接客強化は重要ですが、日本人客が後回しになってしまうと本末転倒です。
例えば、レジ対応で訪日客に時間がかかる際、日本人客の待機列がストレスになるケースも見られます。
その場での声がけや、受付分担、フロアサポートの配置など、シンプルな工夫でも印象は大きく変わります。
また、訪日客と日本人客で接客フローを分けたり、スタッフの役割分担を明確にしたりすることで、混乱を防ぐことができます。
大切なのは、「どちらにも快適な時間を提供する」という意識。
その視点が、信頼とリピートに繋がります。
5-2.分離導線と空間演出
訪日客と日本人客が混在する売場では、スムーズな動線設計が売上にも影響します。
どちらかが混雑してしまうと、もう一方がストレスを感じて離れてしまうことがあります。
最近では、多言語対応の案内表示や、観光客専用の休憩スペース・ラウンジの設置が注目されています。
これにより、日本人は静かに買い物ができ、訪日客は安心して滞在できる環境が生まれます。
空間のデザインも重要で、視覚的に区切るだけで、心理的な安心感を与えることができます。
例えば、和風とモダンを併用したゾーニングなど、演出次第で居心地は大きく変わります。
「分けること」は、おもてなしの形を整える手段です。
6.訪日客戦略のこれから
インバウンド市場は今後も拡大が見込まれており、訪日客の行動に寄り添った段階的なプロモーション設計が不可欠です。
とくに2025年は、中華圏だけでなく東南アジアや欧米圏の動きにも注目が集まっています。
ターゲットを明確にし、訪日前・滞在中・帰国後のフェーズごとに施策を展開することで、単なる売上ではなく、ブランド体験として記憶に残るコミュニケーションが生まれます。
訪日客を惹きつけるために、以下のポイントを意識することが大切です。
・ターゲット国を絞り、文化・ニーズを理解する
・SNSや現地広告で「指名買い」を促進
・店頭では日本語POPや多言語対応を併用
・デザインは“伝わる”を軸に構成する
・大容量や小分けセットで購買を後押し
・帰国後の口コミやSNS投稿をリピーター化へ導く
・日本人客とのバランスを考えた接客と導線設計
一過性ではなく、継続的な来訪と信頼を生むプロモーションこそが、これからのインバウンド戦略の核になります。
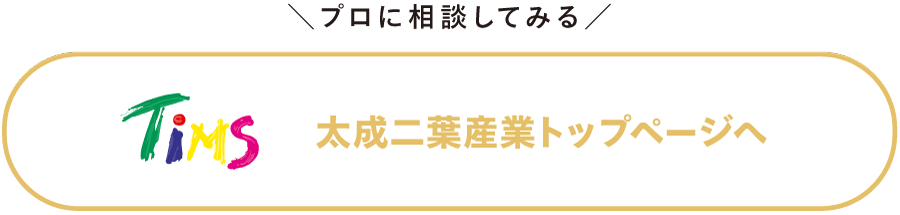
7.よくある質問
Q1:訪日客へのプロモーションは、いつのタイミングが一番効果的ですか?
A:最も効果的なのは「訪日前」のタイミングです。
訪日客の多くは、旅行前にSNSや口コミ、動画などで情報収集をしています。特に中国や台湾などでは「指名買い」が一般的で、買う商品をあらかじめ決めてから来日する傾向があります。
旅行前に商品の存在を知ってもらい、欲しいリストに入れてもらうことが、購買へ直結するため、訪日前の情報発信が非常に重要です。
Q2:訪日客向けのPOPは全て多言語対応にすべきですか?
A:すべてを多言語化する必要はありません。
実は、日本語POPでも十分に効果があるケースがあります。日本語表記は「本場で買っている」という信頼感を与え、日本らしさを演出するツールとしても有効です。
ただし、商品名や使い方など重要な情報は、英語や中国語を併記することで、より親切な売場になります。
「伝える」だけでなく「信頼される」売場づくりがポイントです。
Q3:訪日客と日本人客、両方に満足してもらうにはどうすればいいですか?
A:接客や導線を分けるなど、空間づくりの工夫が必要です。
訪日客に丁寧な対応をした結果、日本人客が不満を感じるケースもあります。専用レーンの設置やラウンジの導入、表示サインの工夫などで混雑を緩和し、両者がストレスなく過ごせる環境を整えることが大切です。
「分ける配慮」が、どちらのお客様にも居心地のよさを提供します。
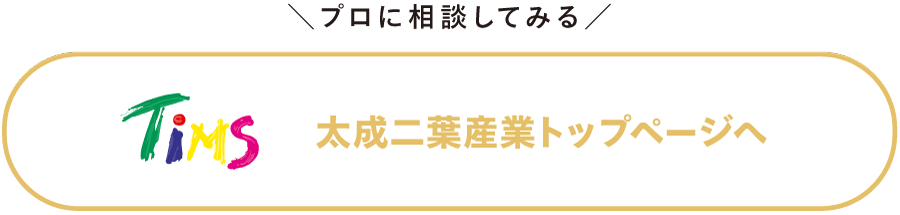
最後までお読みいただきありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。
太成二葉産業へのお問い合わせはこちらから。